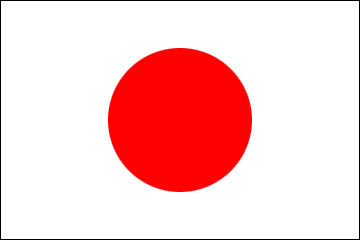ルクセンブルク国民議会選挙制度
1.定数: 60名(1院制)
2.任期: 5年、解散有り
3.選挙区: 以下の4選挙区
・南部選挙区(「Esch-sur-Alzette」「Capellen」州): 定数23名
・東部選挙区(「Grevenmacher」「Remich」「Echternach」州): 定数7名
・中部選挙区(「Luxembourg」「Mersch」州): 定数21名
・北部選挙区(「Diekirch」「Redange」「Wiltz」「Clervaux」「Vianden」州): 定数9名
4.選挙権: 「ルク」在住の参政権を有する18歳以上のルクセンブルク人(選挙法第1条)
5.被選挙権: 「ルク」在住の参政権を有する18歳以上のルクセンブルク人(同第127条)
6.投票義務:
選挙人名簿に登録されている者について、投票が義務となっており、代理人をたてることはできない。正当な理由無くして投票しなかった者は罰金を科せられる。なお、75歳以上の場合、また、国外居住者及び健康上の理由で投票に行けない者のために、郵送投票が認められている。
7.選挙方式:(名簿変動式比例代表制)
(1)各政党は、各選挙区において候補者名簿を提出(各政党が各選挙区において名簿に掲載する候補者数は、当該選挙区の議員定数を上回ってはならない)。
(2)選挙人は、同人が登録された選挙区における議員定数と同数の票数を有している。(例:東部選挙区の場合7票)投票は、政党に対してか、または立候補者本人に対して行うが、その両方を同時に行うことはできない。
政党に投票する場合(リスト投票)は、その政党の全候補者がそれぞれ一票を得ることとなる。
立候補者本人に投票する場合は、一候補者あたりは最大2票しか投票できないが、異なった政党にまたがって投票することができる。
8.議席配分:
選挙区ごとの政党得票数(=各政党の候補者名簿の候補者が獲得した票の合計)に応じて、以下の計算に従い各政党に議席数を配分する。
(1)(選挙区の有効投票総数)÷(選挙区の議席数+1)= (1)(小数点以下、四捨五入)
(選挙区の政党得票数)÷ (1) = 議席数(小数点以下を切捨てた整数の値)
(2)上記(1)の配分後、残りが生じる場合
(選挙区の政党得票数)÷((1)で 配分された議席数+1)の値が大きい政党順に残りの議席を配分する。
9.当選者の決定:
各政党の議席数の配分内で、同政党の候補者名簿に掲載された候補者の中で最も得票数が大きい者から順に当選。同数の場合には、当該選挙管理委員長の抽選により当選者を決定。(各政党の候補者名簿上の順位は当選には無関係)
10.行政府と立法府の兼職禁止:
当選者が閣僚等、政府のメンバーとなった場合には、その者は議員資格を失い、当該選挙区の当該政党の候補者名簿の次点候補が繰り上げ当選する。(一度政府のメンバーになった後に、閣僚を辞任した場合には、出身政党の当該選挙区候補者名簿の第1位次点候補者となり、同名簿の中の議員がなんらかの理由で議員資格を失った場合に繰り上げ当選することとなる。
また、国家諮問院(Conseil d'Etat)及び司法等との兼職もできない。
11.国会議員と欧州議員:
政党の方針として、兼職を禁止しているので、両方に立候補し、双方に当選した場合には、本人がいずれかを選択する。
12.選挙関連法:
(1)憲法第4章51条~74条
議会制民主制、定員、普通選挙、比例代表制選挙区、任期等の基本につき規定
(2)2003年2月18日選挙法改正
<主な改正点>
・選挙義務の維持
・パナシャージュ方式(複数政党候補者連記式)の維持
・選挙権、被選挙権年齢の引き下げ(21→18歳)
・投票義務年齢上限の引き上げ(70→75歳)
13.選挙費用の還付・交付
各政党が選挙キャンペーンに用いるポスター貼付の費用については、最低でも選挙区の有効投票が5%を超えることが証明される場合、国から各政党・団体に対して還付される。
選挙支援金については、全ての選挙区にて候補者リストを提出している政党・団体であって、最低でも1議席獲得した政党乃至団体に対して支給される(欧州議会選挙の場合には、候補者名簿を提出し、最低5%の得票を得た場合)。
・1-4名の議席確保=5万ユーロ
・5-7 〃 =10万ユーロ
・8-11 〃 =15万ユーロ
・12 〃 =20万ユーロ、1名増える毎に1万ユーロ上乗せ。
【投票用紙イメージ】
●選挙区(circonscription)の議席数までの票数を有する。(下の例の場合、中央選挙区では9議席となっているので、投票人は、9票まで投票することができる。)
●「リスト投票」方式:各政党名の○印を埋めることによって、同党(=同党の全候補に1票)に投票する。
●「パナシャージュ方式」:政党をまたがって、希望の候補者名脇の□に×または+を付けて投票し(1候補者あたり最大2個まで)、最大で選挙区議席定数まで投票できる。
1.リスト投票(政党への投票で政党の○印を埋めることにより、同政党内の全候補者に1票ずつ投票したことと同義になる。)

2.パナシャージュ方式(政党をまたがって、選挙区定数まで(一候補2票まで)□に×ないし+を付して投票することができる)

II.選挙後の組閣手続
1.選挙後の組閣手続についての規定は無く、暗黙の合意によって行われている。
選挙で過半数の議席を占めた政党が内閣を構成するが、当国選挙制度からすれば、単一の政党が過半数を占めることはなく、連立政権によって構成されている。
2.選挙の翌日、内閣は総辞職する(首相が大公殿下に報告する)。大公殿下は、新内閣が成立するまでの間、辞職した内閣に日常政務の処理を委任する。
3.大公殿下は、通常最も多くの議席を獲得した政党の筆頭者を、新内閣の「組閣役(formateur)に指名する。組閣役は、新内閣の構成に務める任務を負う。(組閣役は、各政党との協議を行うが、従来より、連立政権のため、獲得議席数が多い第2の政党との協議に重点を置く)
4.連立に合意した政党は、政策の調整、大臣ポストの割り振り等につき組閣役と協議する。通常、各党の大臣ポストの数は、その獲得議席数の割合に応じて決定される。大臣ポストの割り振りが決められた後、連立の各党は、党内で大臣の人選を行うが、通常、個人としての獲得票数が多い者が大臣となる。
5.組閣役は、連立政党との交渉結果を大公殿下に報告し、認証を得たのち、大公令を発布、新内閣が組閣される。
(憲法上、大公は、閣僚についての絶対的な任命権を有しているが、実態上は、閣僚は大公殿下のみならず議会の過半数の信任を得なければならないとの民主主義の原則による制限を受けている。大公殿下は、選挙の結果を尊重して、首相を任命し、首相は、議会の承認が得られることを念頭に、閣僚を報告する。大公殿下は、首相の提出する閣僚を承認し、大臣の任命手続を行う。